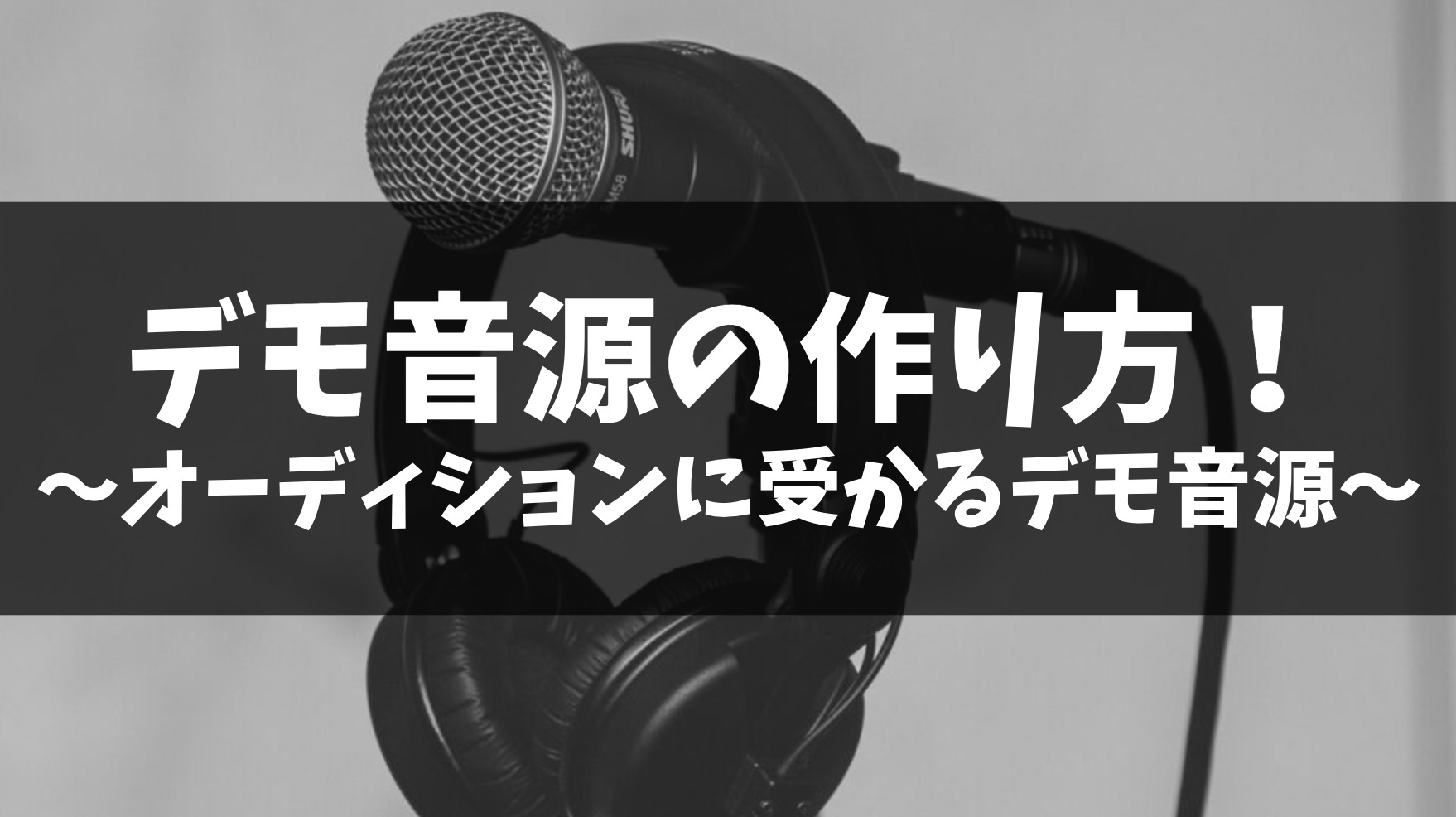音楽制作のやり方6ステップ!必要な機材やポイントも合わせて解説。
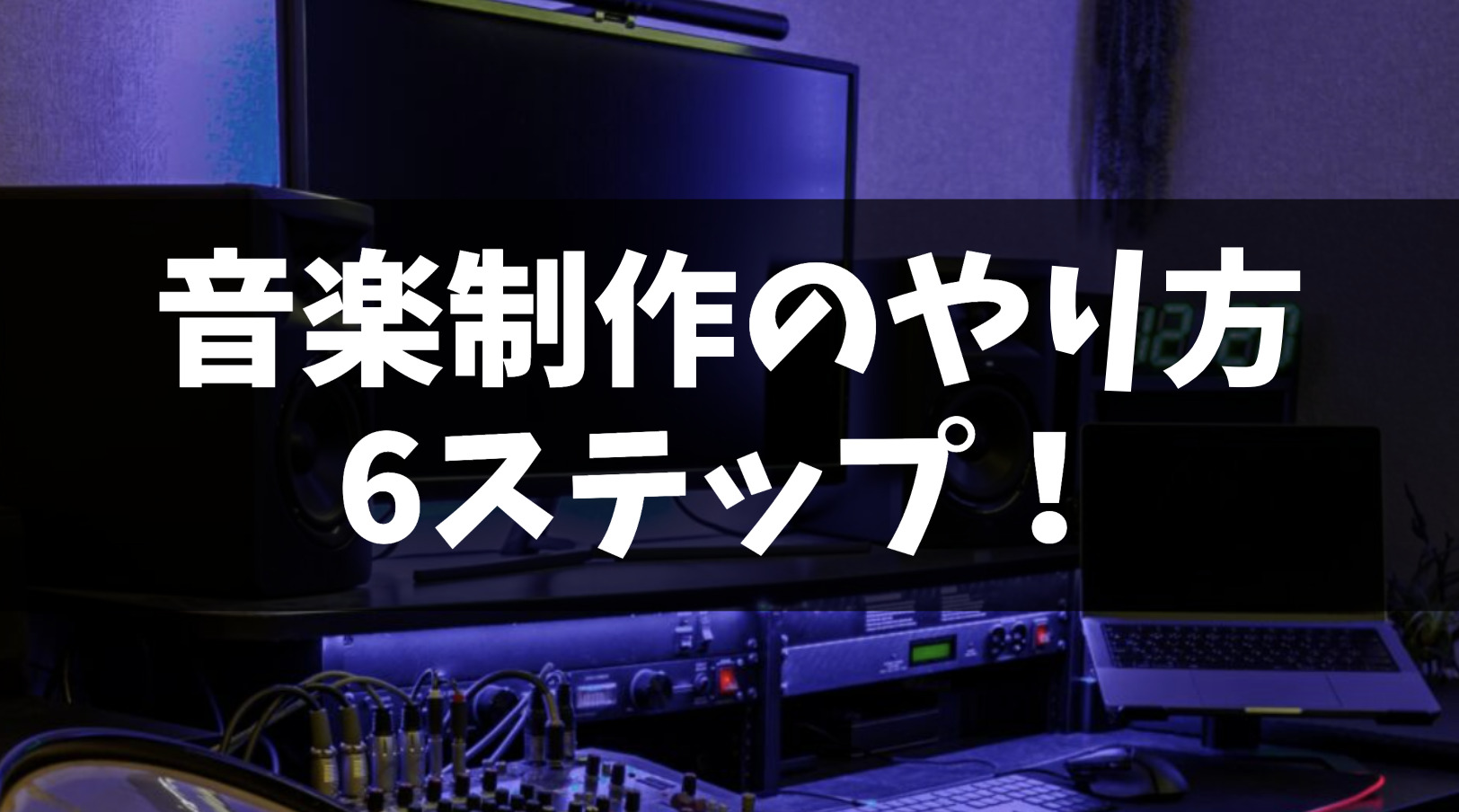
曲のコピーができるようになると、自分で曲を作ってみたいと思う人も多いでしょう。
しかし、初めてだと「何から初めていいのかわからない」「何が必要なのかわからない」と悩んでしまいますよね。
そこで本記事では、音楽制作のやり方や必要な機材について詳しく解説します。
音楽制作とは
音楽制作とは、作詞・作曲からレコーディング、ミキシング・マスタリングなど、楽曲が出来上がるまでの工程を指します。
歌の入っていない音源までを作る場合や、ミキシング・マスタリング作業を行わずに曲作りのみを指す場合も。
また、個人が作ったり楽曲制作会社が作ったりと、曲を作る人も状況によってさまざまです。
音楽制作のやり方は主に3種類

音楽制作のやり方には、主に以下の3つの方法があります。
- メロディーから作る方法
- 歌詞から作る方法
- コードから作る方法
それぞれ詳しくみていきましょう。
メロディーから作る方法
一番わかりやすいのは、メロディーから作る方法です。
楽器を使用して作ることもできますし、声や鼻歌でも作ることができるので楽器ができない人にもおすすめ。
メロディーは曲の中心となる要素であり、良いメロディーが最初に思い浮かぶと最終的な曲のイメージが想像しやすくなるというメリットもあります。
しかし、メロディーに合ったコードをつけるのは意外と難しいため、楽器ができる人はコードから作ることも少なくありません。
歌詞から作る方法
メロディと同じ様に、曲の中心となる要素が「歌詞」です。
実体験をもとに作ることもあれば、想像をもとに作ることもあります。いずれにしろ歌詞には、なんらかの想いやメッセージが詰まっているので、歌詞を先に作ると曲のイメージを固めやすいでしょう。
コードから作る方法
コードとは、複数の音が同時に響いているものを指し、和音とも呼びます。
“C”や”Dm”のようにアルファベットで表記され、メロディーを支える役割のため、曲には欠かせません。
コードから作る場合はピアノやギターなど、コードを鳴らせる楽器を使うのが一般的です。
コードを先に作っておくとその後メロディが作りやすくなりますが、楽器ができないとコードから作るのは難しいでしょう。
音楽制作の具体的なやり方6ステップ

ここからは具体的な音楽制作のやり方について解説します。
以下の6つの手順に沿って、曲を作っていきましょう。
- メロディーやコードなど曲の中心になるものを作る
- 1で作ったものを装飾する要素を加える
- 構成・展開を考える
- アレンジを考える
- レコーディングする
- ミキシング・マスタリング作業をする
ステップ1:メロディーやコードなど曲の中心になるものを作る
まずは曲の中心となるものを作りましょう。
曲にはある程度の長さや展開が必要ですが、最初から一気に完成形を作るのはとても大変です。そのため、初めは曲作りのきっかけとなる小さなパーツから考えましょう。
何を曲の中心にするかは人それぞれです。
先に解説した3つの方法を参考に、自分にあった方法を選んでください。
ステップ2:ステップ1で作ったものを装飾する要素を加える
曲作りのきっかけになるもの、曲の中心となるものが作れたら、それを装飾していきます。
例えば、メロディから考えたのならそれを支えるコードを。メロディとコードができたら、リズムをつける、といった感じです。
最初に考えた小さなパーツに肉付けし、少しずつ曲に近づけていきましょう。
ステップ3:構成・展開を考える
メロディ、コード、リズムが揃った状態で、ある程度の長さができたらその後の展開を考えましょう。
曲はイントロやAメロ、サビ、Bメロ、アウトロなどいくつかの展開が組み合わさってできており、これらの展開が少ないと退屈な曲になりがちです。
最初に作ったパートから繋がる新しいメロディーを考える、リズムをがらっと変えてみる、など曲全体を通して聴いたときにリスナーが飽きないような展開を考えましょう。
ステップ4:アレンジを考える
構成も出来上がり曲として形になったら、アレンジを考えましょう。
曲を作っている最中は「Aメロだけ」や「サビだけ」など、細かいパーツに注目しがちです。曲として形になってから全体を通して聴くことで、アレンジしたほうがいい箇所が見えてきます。
例えば「1番のAメロと2番のAメロは少しコードを変えた方がいい」「最後のサビは盛り上がるようにドラムパターンを変えたほうがいい」などです。
ステップ5:レコーディングする
アレンジも終わり曲が完成したら、レコーディングをしましょう。レコーディングはスタジオを借りてする場合と、自分で必要な機材を揃えてする場合があります。
スタジオを借りてレコーディングする場合、クオリティは高くなる一方で費用は高くなりがちです。自分で機材を揃えてレコーディングする場合、最初に機材を揃える費用はかかりますが、それ以降は基本的にかかりません。
今作っている曲にどれだけお金をかけられるのか、今後も音楽制作を頻繁に行うのかなどを考えて自分にあった方法を選びましょう。
ステップ6:ミキシング・マスタリング作業をする
ミキシング・マスタリングとは、レコーディングした後に、楽器一つ一つの音量バランスや、曲ごとの音量バランスを調整する作業です。
実際にレコーディングしてみるとわかりますが、ただ演奏の音を録っただけでは、プロの楽曲のようにはなりません。
ミキシング・マスタリング作業をすることで、各楽器の音がクリアに聴こえるようになったり、迫力ある音圧が出たりします。
音楽制作に必要なもの

昔は音楽制作をするためには、スタジオを借りてレコーディングする必要がありました。しかし最近では、必要な機材を揃えれば、個人でも音楽制作は可能です。
具体的に、個人で音楽制作をするにはどのような機材が必要なのか解説します。
楽器
楽器があると、曲を作るときもレコーディングをするときもとてもスムーズです。
最近は、実際に演奏せずに音楽制作ソフトを使って楽器の音を再現することもありますが、何か一つは演奏できる楽器がある方がよいでしょう。
演奏しながらのほうが曲のイメージが湧きやすいですし、ソフトで再現した音よりもリアルだからです。
パソコン
個人で音楽制作を行う場合、パソコンは欠かせません。
レコーディングからミキシング・マスタリングまでは、パソコンを使って作業するからです。
なかにはスマートフォンで音楽制作を行っている人もいますが、本格的な曲を作りたいのであればパソコンを使用しましょう。
録音機器
パソコンに音を録音するためには「オーディオインターフェイス」という録音機器が必要です。
オーディオインターフェイスをパソコンに繋ぐことで、マイクや楽器をレコーディングできるようになります。
値段はさまざまですが、初心者向けのものは1万円〜2万円程度のものが多いです。
DAWソフト
DAWソフトとは、パソコンで録音や録音したデータの編集などを行うためのソフトです。
DAWソフトにはさまざまな種類があるため、価格や機能、使用しているパソコンとの互換性などを確認しながら選ぶようにしましょう。
無料のものや、オーディオインターフェイスに付属しているものもあります。
初心者が音楽制作を上達させるポイント

音楽制作のやり方や必要な機材がわかっても、最初から良い曲を作るのはとても難しいです。
上達の一番のコツは、たくさん曲を作ること。
ここで解説するポイントを意識し、たくさん曲を作ってみましょう。
色々な曲を聴く
曲を聴くことは、自分で演奏したり作ったりすることと同じくらい大切です。
普段はあまり聴かないジャンルなどにも積極的に触れ、自分の引き出しを増やしていきましょう。
いつも聴いてる曲も、なんとなく聴くのではなく「曲の構成に注目する」「特定の楽器に注目する」など、注目する箇所を意識して聴くと新たな発見があります。
コピーしてみる
好きな曲や真似したい曲を決めて、全体をコピーしてみましょう。ここでいうコピーとは演奏できるようになることではなく、DAWで再現することです。
耳コピでもいいですし、難しければ楽譜を買っても構いません。
歌だけでなくギターやドラムなど、曲全体をコピーして再現することで音楽制作に必要なスキルの基礎が身につきます。
本で勉強する
音楽制作に関する本は非常に多く出版されています。人によって作曲の方法は違うので、本を通してさまざまな作曲手法を学んでみてください。
また、音楽理論の本もおすすめです。直接音楽制作に関係なくとも、理論を理解していると作曲に役立つことが多いので、音楽理論の本もぜひ参考にしてみてください。
最初はシンプルに作る
初心者がやりがちなミスが「無駄に複雑にしてしまう」こと。楽器をたくさん重ねたり難しいコードを使ったりすると、なんとなくごまかせてしまうからです。
しかし、こうした曲は全体を通して聴くと、まとまりが無いように聞こえてしまいます。
また曲のイメージが固まりにくく、アレンジの段階などで自分でもどう修正していいかわからなくなってしまうことも。
初心者のうちはメロディーやコード、構成、楽器編成など、できるだけシンプルにするようこころがけましょう。
やり方を学べば初心者でも音楽制作はできる
曲を作ったことがない人からすると、音楽制作はとても難しいことのように感じると思います。
しかし、手順やポイントを押さえれば誰でも音楽制作は可能です。
本記事を参考に、ぜひ音楽制作にチャレンジしてみてください。