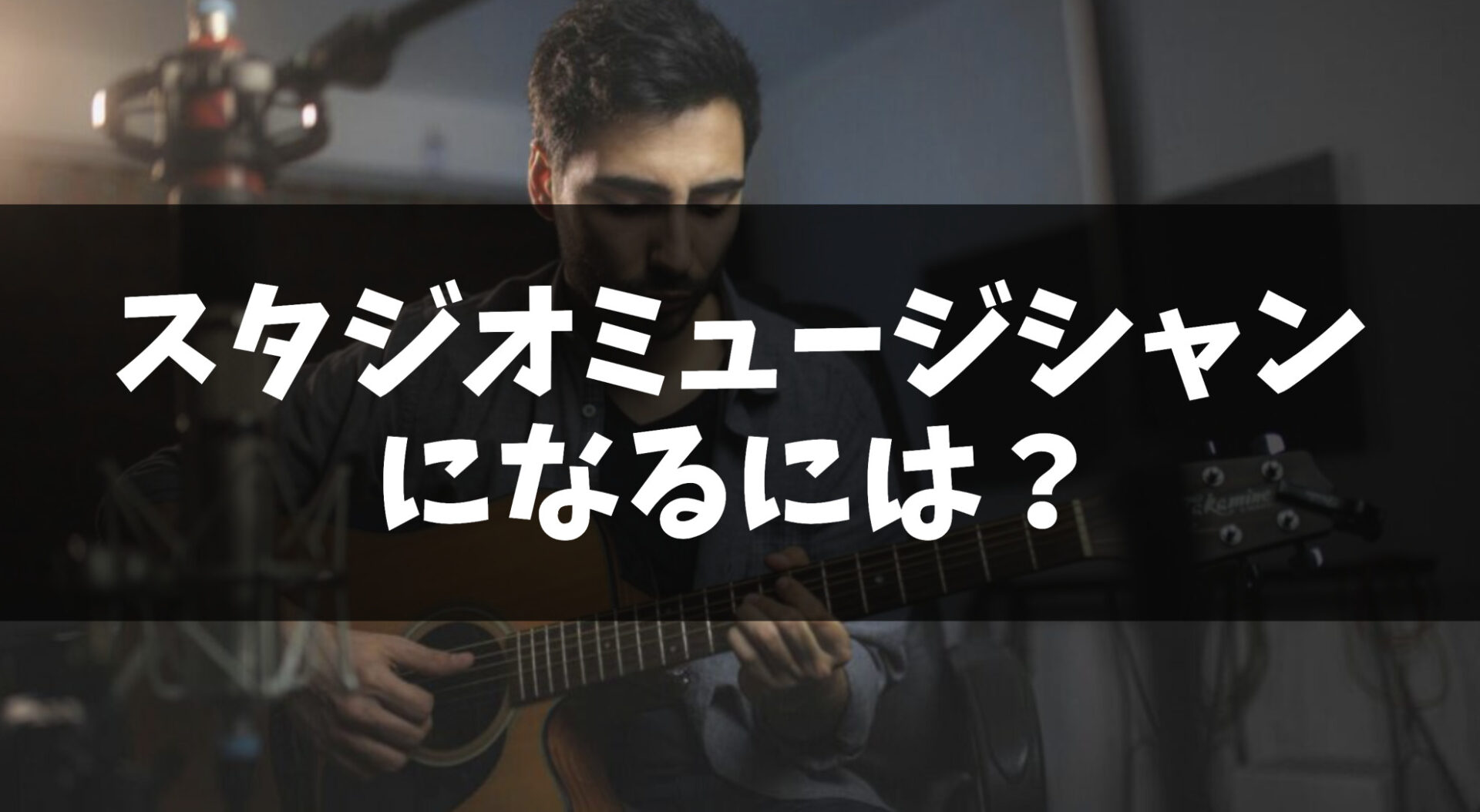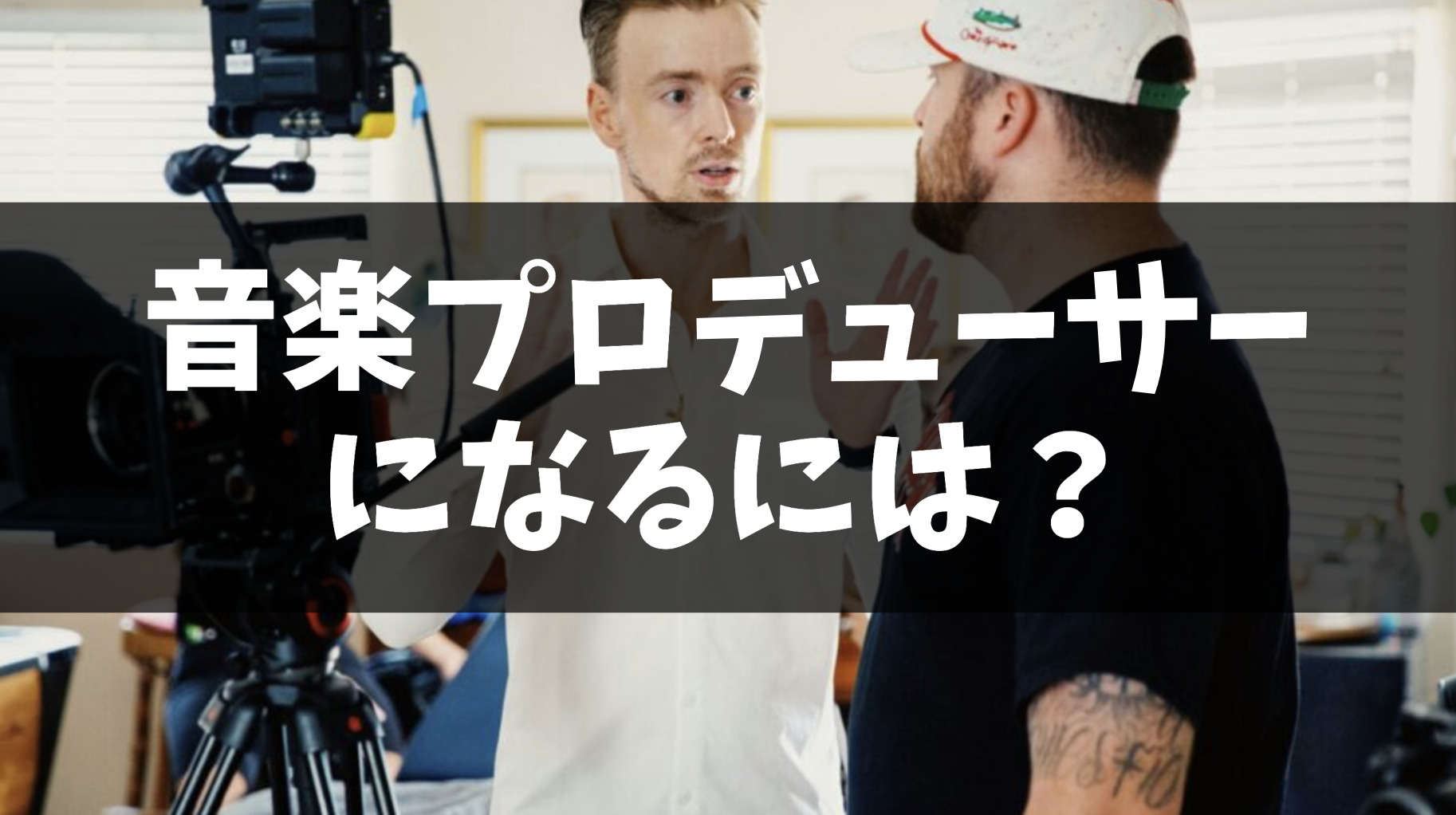ミキサーになるには?必要なスキルや、MA・PAミキサーの違いを解説!
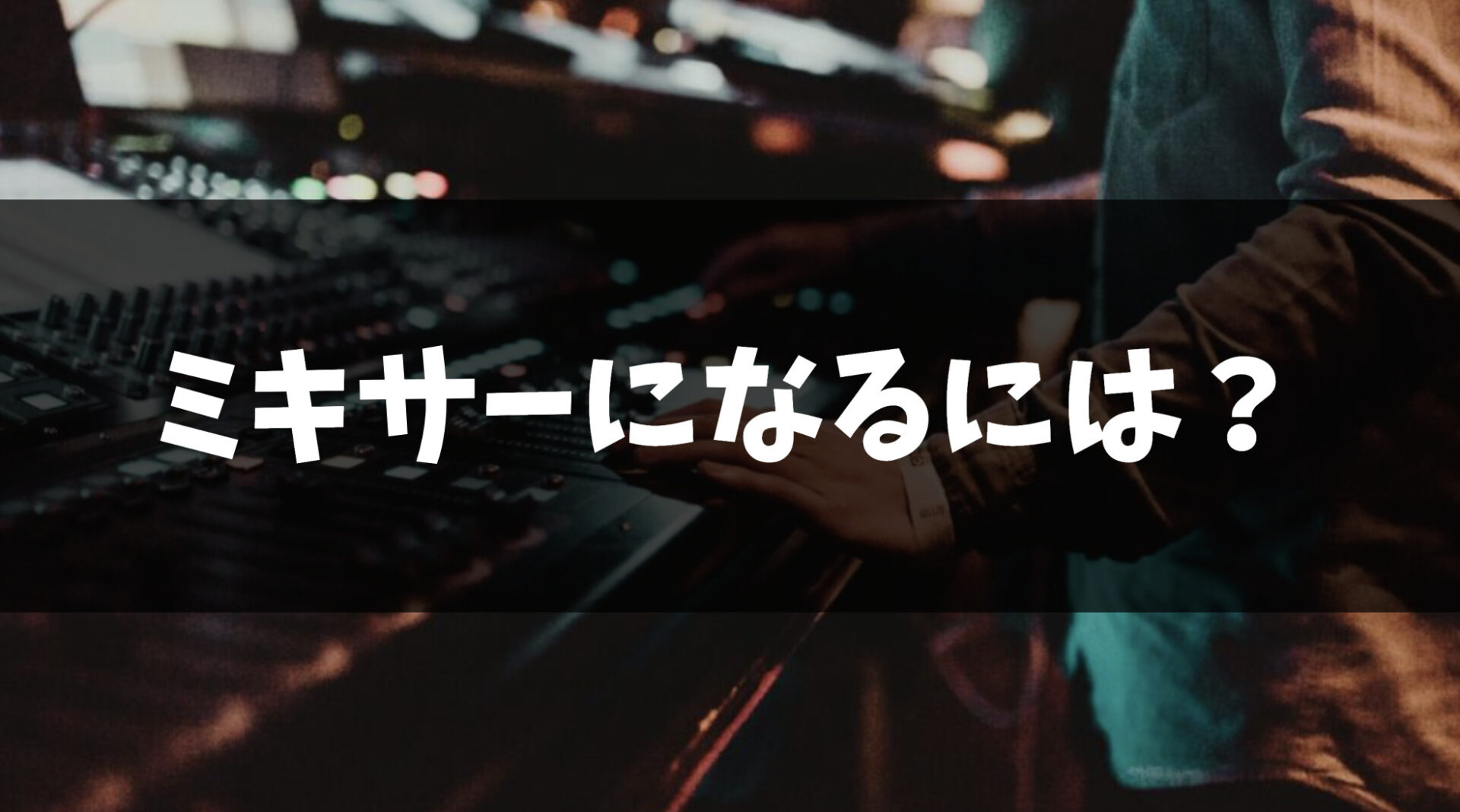
音楽や映像作品において、その音の質や印象に大きな影響を与えているのがミキサーの仕事です。ライブ会場での臨場感あふれるサウンドや、映画での感情を揺さぶる効果音、これらはすべてミキサーの仕事によって生み出され、この仕事に憧れる人も多いです。
しかし「ミキサーになりたい」と思っても、具体的にどんな仕事なのか、どうすれば目指せるのかわからない方も少なくありません。
そこで本記事では、ミキサーを目指す方に向けて仕事内容や、ミキサーになるための具体的な方法、必要なスキルなどについて詳しく解説します。音楽や映像の世界で活躍したいと考えている方は、ぜひ最後までご覧ください。
ミキサーとは?

ミキサーを目指すために、まずはミキサーとはどんな仕事なのかをしっかり把握しておきましょう。具体的な仕事内容はもちろん、ミキサーの種類や働き方、収入などについて知っておくことも大切です。
以降の解説を参考に、ミキサーへの理解を深めてください。
具体的な仕事内容
ミキサーの主な仕事は、複数の音源や楽器の音をバランス良く組み合わせ、聴きやすく魅力的なサウンドに仕上げることです。録音された音源のレベル調整、イコライザーでの音質調整、空間系エフェクトの付加、ダイナミクス処理などを行います。
また、作品のジャンルや目的に合わせて適切な音作りをするため、ディレクターやアーティストとのコミュニケーションも重要な業務です。
スタジオでの収録時には機材のセッティングから担当し、本番では各トラックのレベルを監視しながらリアルタイムで調整します。また、録音後には細かな編集作業やミックスダウン、さらにはマスタリングまでミキサーが担当することも少なくありません。
作品の種類によっては、効果音や環境音の制作・編集を行うこともあります。
PA・MAミキサー、ミックスエンジニアの違い
ミキサーの職種は、基本的に3種類です。まず、PAミキサー(Public Address Mixer)は、コンサートやイベント、ライブハウスなどでの音響を担当します。会場の音響特性を理解し、臨場感ある音を観客に届けるのが役割です。
MAミキサー(Multi Audio Mixer)は、テレビや映画、CM、アニメなどの映像作品を担当し、映像に合わせた効果音やナレーション、BGMなどのミキシングを行います。
一方、ミックスエンジニアは主に音楽制作の分野で活躍し、録音された楽器や声のトラックをバランス良く調整して一つの楽曲に仕上げる仕事です。各楽器の特性を理解し、アーティストの意図を汲み取りながら、魅力的な音楽作品を作り上げます。
働き方・収入・キャリアパス
ミキサーの働き方は、放送局、録音スタジオ、レコード会社、音響関連会社、映像制作会社への就職が一般的です。平均年収は300〜500万円程度ですが、フリーランスで成功した場合は700万円程度になることもあります。
キャリアパスとしては、アシスタントから始まり、経験を積んでチーフミキサー、ディレクターへとステップアップするのが一般的です。最初のうちは機材の運搬や設置、ケーブル配線など体力的な作業も多く、地道な努力が求められるでしょう。
また、ミキサーの経験を活かし、サウンドクリエイターや音響効果スタッフといった他の音響関連職種へ転職するケースもあります。
ミキサーになるには?具体的な4つの行動

ミキサーになるためには、音響技術や音楽についての知識・スキルを身につけながら、実践的な経験を積むことが重要です。ここでは、ミキサーになるための具体的な4つの行動をご紹介します。
ライブハウスやスタジオで働く
ミキサーになるためのもっとも実践的な方法の一つが、ライブハウスやレコーディングスタジオでアルバイトやインターンとして働くことです。初めは機材の運搬や設営、ケーブル配線といった単純作業が多いですが、現場で実際に使われている機材や技術に触れられる貴重な機会となるでしょう。
また、プロのミキサーの仕事ぶりを間近で体験し、理論だけでなく実践的な現場のノウハウを学ぶことができます。
自分でオリジナル作品を作る
自分自身で音楽制作や音響編集を行い、ポートフォリオを作ることも有効な方法です。自主制作映画の音響を担当したり、友人のバンドの曲をミキシングしたり、あるいは自分自身の音楽を作ってミキシング・マスタリングを行ったりするなど、実際に作品を作ることで実践的なスキルを習得できます。
また、作品が増えてくれば、それをポートフォリオとして就職活動や仕事の獲得に活用できますし、インターネット上に公開すれば、仕事のオファーにつながる可能性もあるでしょう。
最近では比較的安価なDAWソフトやオーディオインターフェースを使って、自宅でも高品質な録音や編集が可能になっているので、ぜひ挑戦してみてください。
専門学校に通う
音響や音楽に関する専門学校に通うことで、体系的に必要な知識や技術を学べます。専門学校に通うメリットは、現役のプロから直接指導を受けられるだけでなく、業界で使われている最新の機材や設備を使用できる点です。
また、専門学校には業界とのつながりがあり、インターンシップやアルバイトの紹介、就職支援などのサポートも充実しています。他にも、同じ志を持った仲間との出会いや、共同制作などを通じて人脈を広げられる可能性など、直接仕事につながる機会も豊富です。
音響関連会社などに就職する
音響関連会社に就職してキャリアをスタートさせるのも、一つの方法です。具体的には、テレビ局、ラジオ局、映像制作会社、映画制作会社、レコード会社、レコーディングスタジオ、音響関連会社、MAスタジオ、ポストプロダクション(撮影後の仕上げ作業を専門とする会社)などが就職先として考えられます。
大手の会社では新卒採用を行っているケースもありますが、多くの場合は経験者採用が中心です。そのため、前述のアルバイトやインターン、自主制作などで実績を積んでおくと、採用される可能性が高まるでしょう。
ミキサーになるために必要なスキル・知識
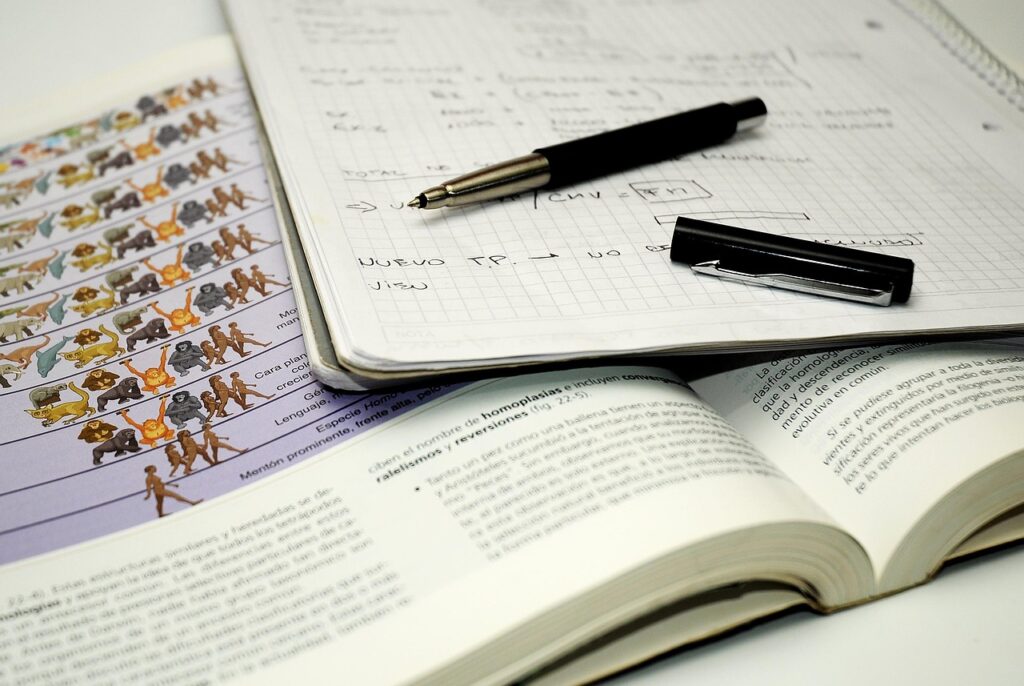
ミキサーとして活躍するには、技術的なスキルだけでなく、音楽的な知識や感性、そしてコミュニケーション能力など多岐にわたる能力が求められます。
ミキサーになるために必要不可欠なスキルと知識について詳しく解説するので、参考にしてください。
音響機器の使用方法
ミキサーの仕事においてもっとも基本となるのが、各種音響機器の使用方法に関する知識と技術です。ミキシングコンソールの操作はもちろん、マイクの種類や特性、適切な設置方法、アンプやスピーカーの特性と配置、各種ケーブルの接続方法など、機材に関する知識が幅広く求められます。
特にPAミキサーになる場合、限られた時間内にセッティングや音量調整を行わなければならないため、素早く正確に機材を操作できる技術が必要です。また、突発的なトラブルにも対応できるよう、機材の仕組みや修理方法についての知識も身につけておきましょう。
ソフトウェアの操作方法
現代のミキサーにとって、DAW(Digital Audio Workstation)といった音楽制作ソフトの操作スキルは必須です。代表的なソフトウェアとしては、Pro Tools、Logic Pro、Cubase、Ableton Live、Digital Performerなどがあります。
また、音響処理用のプラグインソフトについても理解を深め、求めるサウンドに応じて適切に使用できるようにしておきましょう。
優れた聴力
ミキサーにとってもっとも重要な資質の一つが、優れた聴力です。
特に、周波数帯域ごとの特徴を聴き分ける能力は欠かせません。例えば「このボーカルは3kHz付近が出すぎている」「ベースの80Hz周辺にモコモコ感がある」といった具合に、音の問題点を周波数で特定できることが理想的です。
また、空間的な音の広がりや奥行き、音のキャラクターの違いなども聴き分けられるようになると、よりレベルの高いミキシングが行えます。
音響に関する知識
音の性質や伝わり方¥といった、音響に関する知識もミキサーにとって重要な要素です。基本的な音響知識を身に着けておくことで、さまざまな環境での最適な音作りが可能になります。
例えば、部屋の形状や素材による音の反響特性を理解しておけば、それに応じたマイキングやミキシングを行うことが可能です。
さらに、ビットレート、デジタルオーディオの基礎などについても理解しておけば、録音や編集をよりスムーズに行うことができるでしょう。
音楽に関する知識
直接ミキシングに関わる知識に加えて、音楽の知識も身につけておきましょう。
さまざまな音楽ジャンルの特徴や代表的な作品についての知識があると、そのジャンルに求められる音作りがしやすくなります。
さらに、楽器についての知識も重要で、各楽器の音域や音色の特徴、マイキングのポイントなどを理解しておくことで、より効果的な録音やミキシングが可能になるでしょう。
ミキサーに向いている人の特徴

ミキサーになるには技術的なスキルだけでなく、性格や資質も重要です。ここでは、ミキサーに向いている人の特徴を5つのポイントに分けて解説します。
自分自身の特性と照らし合わせてみることで、ミキサーが自身に合っているかを判断する手がかりになるでしょう。
音楽や映像作品が好き
まず何より大切なのは、音楽や映像作品が好きということです。
ミキサーの仕事は、長時間の調整作業や細部へのこだわりが求められる場面も多く、作品に対する気持ちが無ければ仕事を続けるのは難しいでしょう。
また、プライベートの時間も惜しまず音楽や映像作品に触れられる熱量も必要です。仕事以外の時間でも音楽や映像に興味を持ち、積極的に学べるかどうかは、ミキサーとしてのキャリアを大きく左右します。
音楽的センスや感性が優れている
ミキサーには技術的な知識と並んで、音楽的センスや感性が求められます。どんなに高度な機材や技術を持っていても、音楽の本質を理解し、作品に適した音作りができなければ、プロのミキサーとして成功することは難しいでしょう。
具体的には、音のバランス感覚や空間的な広がりの表現力、楽曲の展開に合わせた緩急のつけ方など、数値では表せない感覚的な部分での判断力が必要です。これらのセンスは生まれ持った才能の部分もありますが、多くの音楽を聴き、実践を重ねれば磨くことができます。
機材やソフトウェアの扱いが得意
ミキサーの仕事では、さまざまな機材やソフトウェアを使いこなす必要があります。新しい機器やソフトウェアに対する興味と、それらを習得する意欲がある人は、ミキサーに向いていると言えるでしょう。
また、音響機器の進化は非常に速いため、常に新しい知識を吸収し続ける学習意欲も欠かせません。
集中力がある
ミキサーの仕事では、長時間にわたって細かな音の調整を行ったり、複雑な音源を整理したりする作業が続きます。
特にライブミキシングでは、演奏中のすべての楽器や声をリアルタイムで監視し、瞬時に適切な調整を行わなければなりません。また、録音やポストプロダクションの現場でも、微細な音の違いを聞き分け、必要な修正を的確に行うための集中力が必要です。
そのため、高い集中力を持ち、細部に対する注意力が高い人はミキサーに向いていると言えるでしょう。
コミュニケーション能力が高い
ミキサーは単独で作業することも多いですが、基本的にはアーティストやディレクター、プロデューサー、エンジニア、その他のスタッフと協力して作品を作り上げます。そのため、円滑に仕事を進めるには、優れたコミュニケーション能力が欠かせません。
特に重要なのは、アーティストやディレクターの抽象的な要望を、具体的な表現に落とし込んで伝える能力です。
また、音楽制作の現場ではときに険悪なムードになることもありますが、そんな中でも冷静さを保ち、円滑なコミュニケーションを取れる人は重宝されます。
ミキサーになるためにおすすめの資格3選
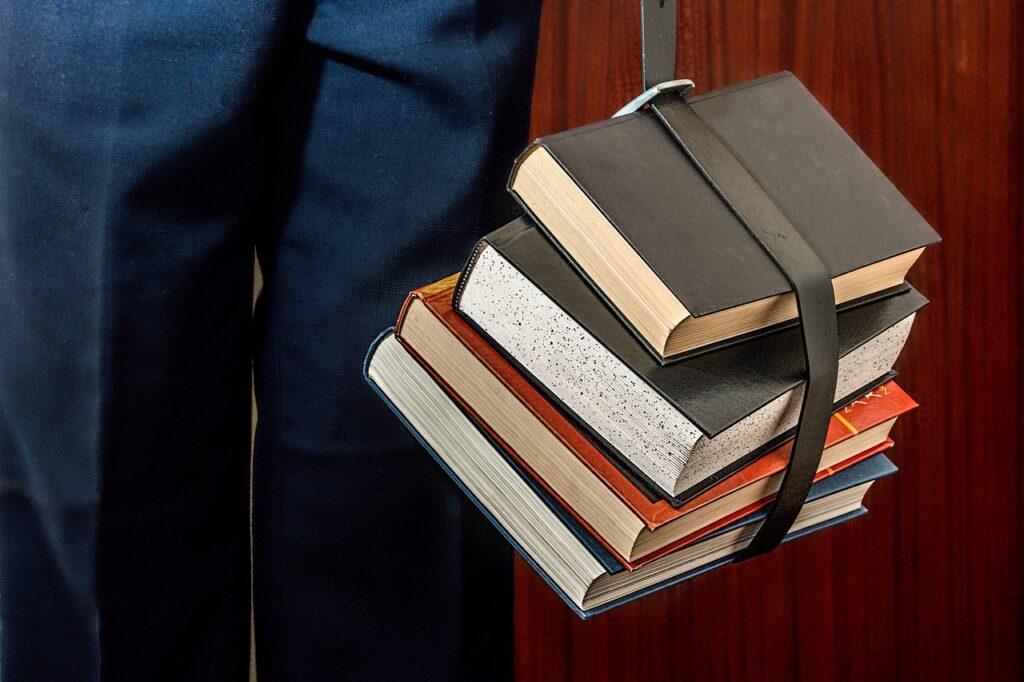
ミキサーになるために必須の資格はありませんが、専門知識や技術を証明する資格を取得することで、就職や仕事の獲得に有利になる可能性があります。
ミキサーを目指す人におすすめの資格を3つ紹介するので、参考にしてください。
映像音響処理技術者資格
映像音響処理技術者資格は、一般社団法人日本ポストプロダクション協会が認定する資格で、映像音響に関する専門知識と技術を証明するものです。
テレビ番組・CM・映画・ネット配信等のコンテンツを手がける映像・音響関連業界で働く際に、最低限知っておくべき知識が出題されます。
誰でも受験でき、合格率は70%程度なので、比較的難易度の低い資格です。試験は毎年6月上旬頃に実施され、受験するには5,500円(税込み)の受験料が必要になります。
MIDI検定
MIDI検定は、一般社団法人音楽電子事業協会が主催する資格で、MIDIやデジタル音楽制作に関する知識を問う検定です。
MIDIとは、電子楽器やコンピューターで作成された音楽情報を共有するための統一規格で、音楽制作には欠かせません。特にミキサーを目指すならMIDIファイルは必ず扱うことになるので、MIDIに関する知識を証明できるMIDI検定を取得しておけばよいアピールになるでしょう。
グレードは4級から1級まであります。4級は講座と検定試験がセットになっており、講座を受講したあとすぐに受験可能です。3級は初級クラス、2級は上級クラスとして設定されているので、できれば2級以上を取得しましょう。
検定受験料は、3級が3,850円、2級1次試験が6,050円、2級2次試験が13,200円、1級が19,800円です。
Pro Tools技術認定試験
Pro Toolsは音楽や映像制作の現場でもっとも広く使われているDAWソフトの一つであり、その操作技術を証明する認定試験が「Pro Tools技術認定試験」です。合格・不合格ではなく、A~Eによってランク分けされ、高いランクに認定されれば就職にも有利に働きます。
特にライブや楽曲制作に携わるPAミキサー、ミックスエンジニアなら、ぜひ受けておきたい試験です。
ミキサーの将来性は?

近年はテレビや映画だけでなく、YouTube・Netflixなどの動画配信、音楽配信、Web広告、駅のデジタルサイネージなど、音響系・映像系作品は増加傾向にあり、ミキサーの活躍の場は確実に広がっています。
そのため、基本的にはミキサーは将来性のある仕事といえるでしょう。
しかし、ミキサーは基本的に1つの作品に対して少人数で対応することが多く、コンテンツ数の増加に比例して求人が増えるわけではありません。
ミキサーとして仕事を得るためには、他の人にはない独自のスキルや、機械では代替できない創造的なセンスをアピールする必要があるでしょう。
ミキサーになるには高いスキルと努力が必要

本記事では、ミキサーの仕事内容やミキサーになるための方法などについて、詳しく解説しました。
ミキサーには映像や音楽作品の音響を担当するMAミキサーと、ライブやイベントでリアルタイムに音響を担当するPAミキサー、主に音楽制作を担当するミックスエンジニアの2種類があります。
ミキサーになるためには、ライブハウスやスタジオでのアルバイト、専門学校での学習、音響関連会社への就職などさまざまなアプローチがありますが、どのような方法でミキサーを目指すにしろ、専門スキルや音楽的センスが必要不可欠です。
本記事の内容を参考に、必要な能力や特性を高め、ミキサーを目指しましょう。